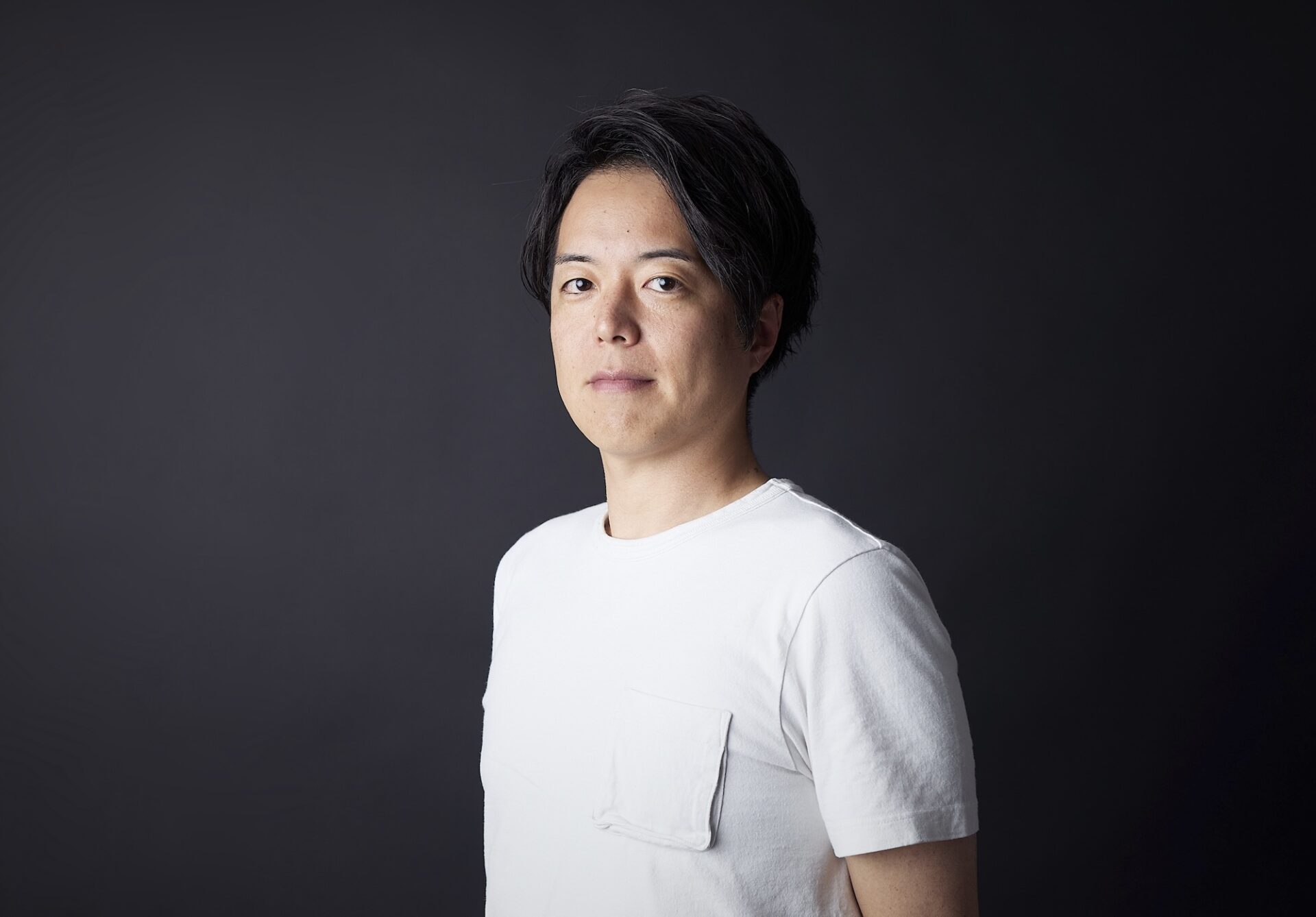(写真左:深津 大貴、写真右:小笠原 亮)
日本大学校友会の担当者様から「卒業生、学生、教職員など日本大学に関わる方々への応援メッセージとなるような“とにかく良いものを、心に届くものをつくりたい”」という想いをお預かりしたのは2024年春。一連の不祥事があった中で、日本大学(以下、日大)の良さをあらためて感じていただけるような映像づくりを目指し、エレファントストーンがご一緒させていただきました。
13名の日大卒業生インタビューと、それを一つにまとめた本編が『道をひらく人』シリーズとして公開。これらの制作に、現場ディレクターとして携わった深津と小笠原の2名にインタビューをしました。
──二人はこのプロジェクトの初期段階から参画していたと伺いました。最初に話を聞いた時は、どんな心境でしたか?

深津「母校のプロジェクトでもありますし、挑戦したいと思っていたドキュメンタリーでもあったので、率直に嬉しかったです。お客様の“一連の不祥事が続いている中で、日大に関わる人たちの背中を押していきたい”という想いを受け取って、これは僕自身も目指したい視聴者のひとりであると認識しました。
大学に在籍していた当時、僕も『日大さん大変そうだね』と言われていた立場なんですよ。だからこそ、日大校友会のみなさんの気持ちに強く共感しましたし、ぜひ制作したいと思いました」
小笠原「僕は不祥事についてはニュースで目にしていましたが、日大に対しては偏見もなくフラットに捉えていました。
ドキュメンタリー映像はこれまでも制作してきていますが、このプロジェクトは自分にとっても大きな節目になるような気がしていましたね。嶺さん(=本プロジェクトの統括)の指揮のもと、これまで以上のレベルでお客様の想いにお応えしていこうと、プロジェクト編成にも力が入っていましたから。
もちろんプレッシャーもありましたが、このプロジェクトの経験を通してディレクターとしても成長できると感じていました」
──日大卒業生13名のインタビューを進めていくにあたって、シリーズとしての統一感を担保するために最初に撮影時の共通ルールを決定したと伺いました。
深津「そうです。今回のプロジェクトはディレクター5人、カメラマン2人という体制でした。スタッフの人数が多いとクオリティコントロールが難しくなるのですが、シリーズを通して一定のクオリティを保つため、そしてルックの統一感を生むためのルールを決めました」
小笠原「前例がないので、このルールをどうやって決めていくのかも手探りでしたね」
──そうだったんですね。そのルールづくりはどんな風に進めていったんですか?
小笠原「企画をベースに、それをどう“画”に落とし込んでいくかを考えていきました。当初の企画は【日はまた昇る】をテーマとしていたので、朝のシーンが綺麗に見えるようなルックがいいんじゃないかと話していましたね。目指したいイメージ映像がこちらでした」
小笠原「そこから先輩に『*LUTをつくった方がいい』とアドバイスをいただいて、どうしたらそのクオリティに到達できるのか、ディレクターのメンバーで話すところからスタートしていきました」
*LUT=Lookup Tableの略:映像の色味を数式によって変換するカラープリセット

小笠原「LUTだけではなくて、レンズや構図をどうするかはパートナーであるカメラマンにも相談をしていました。具体的には、カメラマンが変わっても距離感が統一されるように、ズームレンズではなく単焦点レンズを採用すると決めました。その上で『こういうシーンは全身を映しましょう』と構図のルールもつくりましたね」
※以下、ルール化された方針資料の一部
深津「ルックや撮り方を決めた後に、時間は限られていたんですがテスト撮影もしたんですよね。普段のプロジェクトではあまりやらないのですが、日大へロケハン行って、実際に撮影をさせていただく場所で光の当たり方を見たり、カメラや複数種類のレンズを試したりして、最終的な機材を決めていきました。
その撮影素材をポストプロダクションのスタジオに持っていって、プロのカラーリストとテスト撮影をしたカメラマン、嶺さん、そして僕とで参考映像と照らし合わせながらどういう色にしていくかも調整しました。そういった細かい設定を決めて狙って撮っているのが、今回のドキュメンタリー映像のポイントかと思います」

──撮影当日に1ミリ単位で細部にこだわっていたことには、お客様もとても驚いていましたよ。
そういったルールを決めた上で撮影に挑んだと思うのですが、13名のインタビュー対象者の年齢やお仕事、活動拠点などすべて異なる中で、撮影する要素・シーンはどんな風に決めていったのでしょうか?
深津「一つずつの映像の全体の流れを仮説でつくっていました。こういう話を聞いて、こういうインサートが入って……みたいなイメージで、あらかじめ想定はするんです。
その上で、13名全員と必ず30分〜1時間の事前打ち合わせの時間を設けていました。
『ドキュメンタリー映像としての完成度を高めるために、こういう要素を撮影させてほしい』『こういう話を具体的にお伺いしたい』というご要望をすべてお伝えした上で、『ここは撮影可能です』『これは難しいです』といった細かい部分のすり合わせをしていました。その方の話を聞いて『じゃあそのシーンを撮りましょう!』となることもありましたね」
──そうだったんですね!
インタビュー対象者との関わりや当日の進め方はそれぞれの現場ディレクターに一任されている部分も大きかったと想像しますが、ドキュメンタリー映像として良い作品をつくるためにご自身がこだわったことはありますか?
深津「インタビュー対象者の活動拠点で撮影をするケースが多かった中で、#07の井上さんは日大のキャンパスで撮影をしました。キャンパスでの撮影である分、撮影できる要素が限定的になってしまうことが想定されたので、井上さんらしい“画づくり”は工夫しました。
井上さんは在学中に、芸術学部の文芸学科から放送学科に転科されているんですよね。そうした中で話される内容と背景の親和性が高まるように、文芸学科時代のインタビューは図書館で、放送学科時代のインタビューは放送室で撮影しています。
また、『撮影日に在学中に取り組んでいた課題を持ってきてください』と、ご依頼をしておきました。そうしたら、文芸学科時代につくっていた刺繍や教授から赤字をもらっている課題のプリントなど、スーツケース1個分くらい持ってきてくださって。そういった資料や素材を映像の中に取り入れさせていただいています」
小笠原「最初に嶺さんの撮影現場に見学に行き、“インタビューされる方にも、何か学びや新たな気づきが得られることが良いインタビューだな”と感じたんですよ。そのために今回は、その人についての理解を深めていく中で自分なりの仮説を立てて『僕はこう思うんですけど、どうですか?』 みたいな聞き方を試してみました。
それが合っていれば相手に気づきを与えられる可能性がありますし、間違っていても訂正してくださって話が展開されていきます。結果的に今までのインタビューよりも、踏み込んだお話を聞くことができたなと思います。
また、僕が撮影を担当した#03の昆布さんについては、お話する内容があんまり見えてない中で“先に撮れるシーンを全部撮る”というやり方をしたんですよ。もちろん事前打ち合わせをしているので、仮説のもと構成や撮影素材、核となりそうな話などは念頭に置いてました。
でも、朝からインタビュー以外のシーンを色々と撮影して信頼関係をつくった上で、最後にインタビューをしたほうが、良いインタビューができると思ったんですよね。正直賭けなところもあったんですが、信頼関係が築けたからこそ伺えたお話もあったと思っています」
──最後に、2024年11月に本編と13名のインタビュー映像が公開されました。プロジェクトを終えた感想をお聞かせください。
小笠原「(各インタビュー撮影を担当したスタッフが異なるため、)完成した映像を見て一番楽しいのは、きっと制作スタッフたちなんじゃないかと思いました。他のディレクターがこんな風に撮っていたんだという発見もありましたし、本編では『自分が撮った言葉がここで使われてる』『(本編を編集した)嶺さんはこうチョイスするんだ』という発見もありました。一番の特等席で、映像を見させてもらってるような感覚でしたね。
この映像は日大の卒業生に限らず、今を生きる人たちに向けたメッセージにもなっていると思います。仕事とか関係なく、友達にも見てほしいなって思う作品になりました」

深津「実際に日大の先輩たちの話を聞いて、学生時代の悩みのようなものが日芸生(=日大芸術学部の学生)のあるあるなんだなと思いましたね。いわゆる“芸術”を目指している学生が多くて、その多くは挫折をしたり、芸術を辞めて別の道を歩んでいったり。学科は違うんですけど、 共感するようなポイントがいくつもありました。そうした中で道を切り拓いていらっしゃる皆さんのお話を聞いて、後輩としても1ディレクターとしても非常に感化されましたし、背中を押されました。
また、日大のキャンパスでの撮影時には、僕が映像を学んでいた頃の教授たちもいたんですよ。映像ディレクターとしての現在の姿を見てもらうことができたことも、本当に印象深い出来事でした」
──お二人ともありがとうございました!
日本大学卒業生ドキュメンタリーシリーズ『道をひらく人』の映像は、こちらからご覧いただけます。
PROJECT
MEMBER
制作メンバー