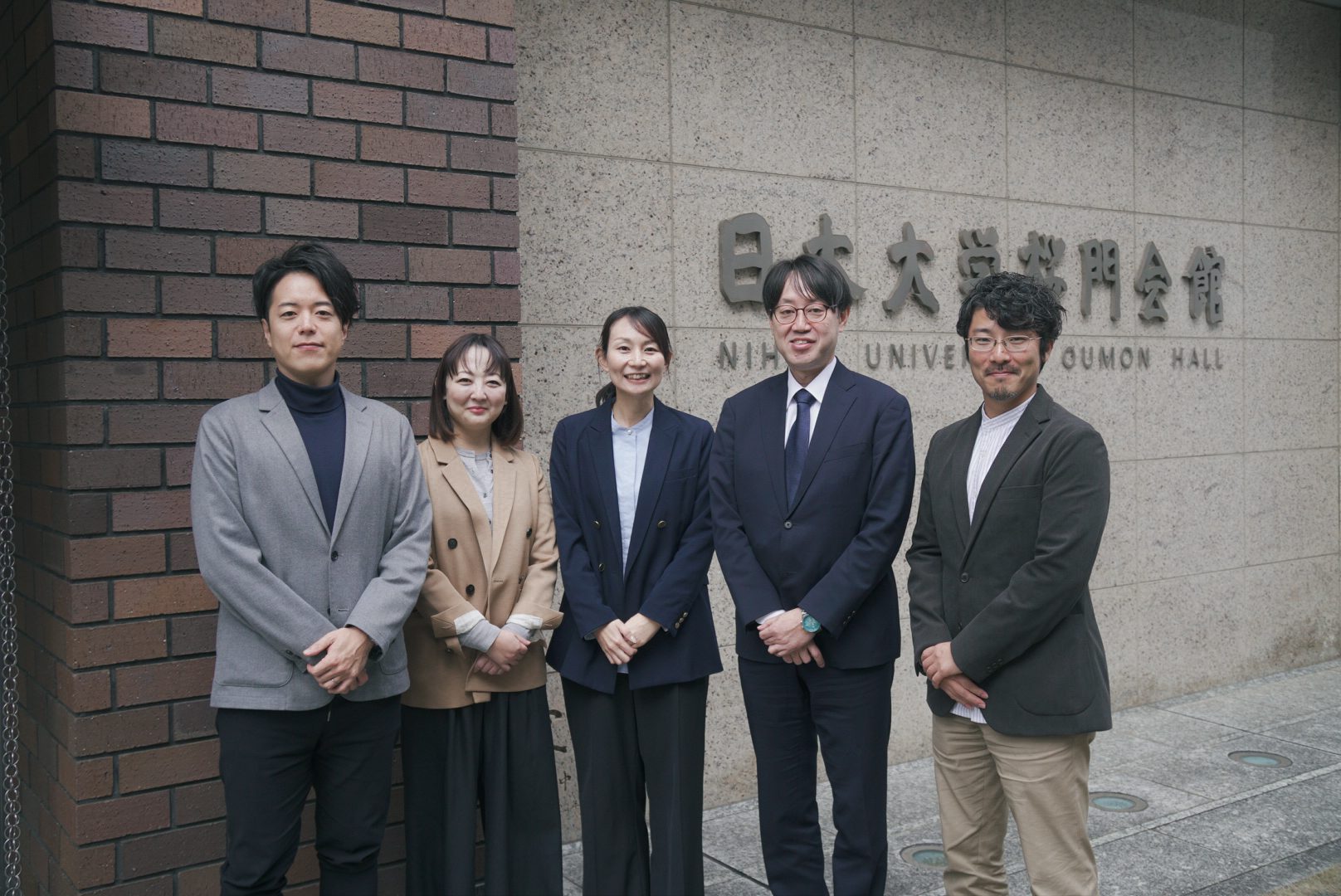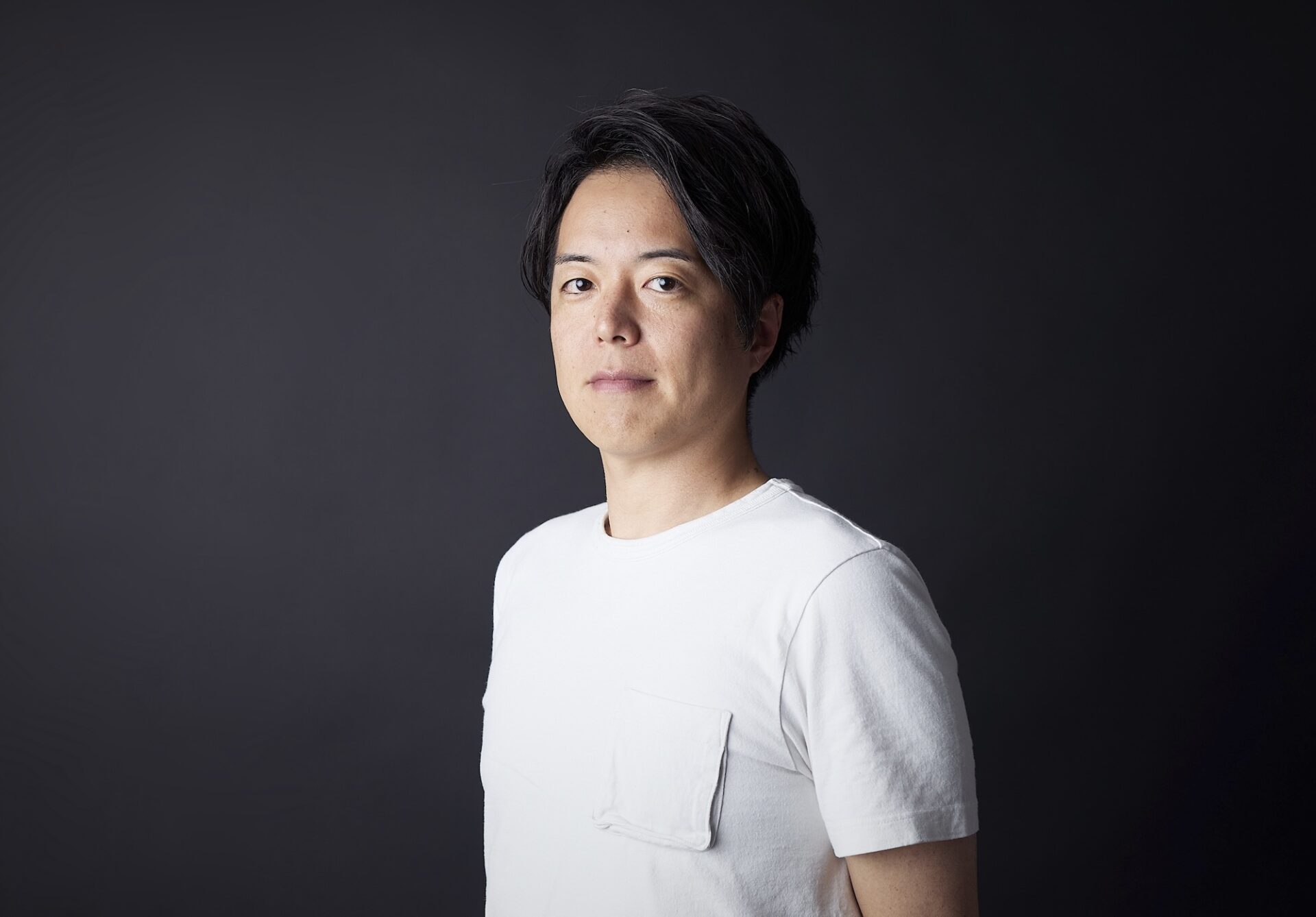多彩な日本大学の卒業生にインタビューをしたドキュメンタリー映像『道をひらく人』。13名の個別編に加えて、それらを1本にまとめた本編が公開されています。
このプロジェクトストーリーでは、本プロジェクトを企画から牽引された日本大学校友会本部事務局 校友課長 真鍋忠伸様、課長補佐 水野綾子様、三角幸代様(以下、敬称略)をお迎えし、弊社から本作品のプロデューサーの伊藤、ディレクターの嶺を交え、5名の対談形式で映像づくりの背景にあった想いや映像の公開に至るまでの道のりを振り返ります。
失われつつあるつながりを、もう一度構築し直したい
──皆さん、本日はよろしくお願いいたします。まずは、そもそも映像づくりのご相談に至った経緯をお伺いできますでしょうか?
真鍋「日本大学(以下、日大)の一連の不祥事があった中で、校友会も昨年の6月に新会長が就任して改革を進めていました。その頃に私は本部の広報課から、校友課に異動してきました。
校友会を支援する校友課では、校友会の会報誌『桜縁』を年2回、日大人と母校を結ぶコミュニケーション誌『KiZUNA(絆)』を年1回、発行しています。『桜縁』では2002年の創刊からこれまで、素敵な卒業生たちを取材してきていて、その中で生まれた日大と卒業生、あるいは卒業生同士のつながりがありました。ただそのつながりも、不祥事を期に失われつつあった気がしたんですよね。
広報課にいた頃から厳しい言葉をたくさんいただきましたし、校友課で仕事をしていても『卒業生だと名乗りたくない』という方もいらっしゃいました。それでも、日大が再生するためには卒業生の力が不可欠だと確信していたので、卒業生とのつながりをもう一度構築し直していきたいと考え、企画したのが映像をつくることでした」
──そうだったのですね!さまざまな手法の中で、なぜ“映像”を選ばれたのでしょうか。

真鍋「まず『桜縁』のバックナンバーを創刊号からすべて読んで、これまでどういう方々を取材してきたのかを紐解いていったんですよね。そして、この人たちにもう一度クローズアップしてつながりを再構築していきたいと思った時に、まだやっていない表現方法といえば、映像だなと思ったんです。
試しに映像を検索しはじめると、古河市のPR動画が思わず住みたくなるような美しさがあり印象的で。その映像を目の当たりにしてから、“とにかく良いものを、心に届くものをつくりたい”と強く思ったんですよね。そこから、インタビュー映像を美しく撮れるような会社を探し始め、校友会役員の方々に説明しました」
──そういった背景で弊社を見つけてお声がけくださったんですね。嬉しいです。ありがとうございます!
真鍋「はい。一連の不祥事があって以降は非難の言葉をいただくことが多く、正直なところ、日大という組織体自体が社会に受け入れられるのかという恐怖が私の中にありました。実際これまでの仕事でお断りをされた経験もあります。
エレファントストーンの伊藤さんは実際に丁寧にいろいろなことを教えてくださったのですが、伊藤さんのその時の対応は非常に心に沁みました。受け入れてくださって本当にありがとうっていう感覚です」
伊藤「今のお話が僕の中での最初のきっかけであり、このプロジェクトの全てです。真鍋さんがお電話でおっしゃった『悔しい』という一言が自分の中で強烈に残っています」
真鍋「私自身だけでなく、私たちの仲間に対して非難の言葉がかかることへの悔しさがありました。なんとかイメージを変えつつ、皆さんの心の癒しになるようにしたいと本気で思っていましたね」

伊藤「当然ながら、断られる方を一概に否定はできませんが、僕としても会社としても、いろいろな物事の見方がある中で、一つの側面だけでそれをすべてだと捉えて判断することがあまり好きじゃないんですよ。
真鍋さんをはじめ日大出身の皆さんが自分なりに積み上げてきて、大切にしているものがあるはずなのに、それを否定するっていう行いが許せなくて。そういうのを、正していきたいと言いますか。その一端だけではなくて、良いところもあるんだと伝えることを、僕も会社もやりたかったんですよね。お客様の誇りをつくると掲げている会社なので、最初に嶺くんに声をかけた時も『僕らがこれをやらなかったらダメでしょ』って伝えていました」
嶺「伊藤は取締役という立場上いつも割とフラットなんですけど、声をかけてもらった時はめちゃくちゃ姿勢が前のめりでしたね(笑)笑顔で『嶺くんにとってもピッタリなプロジェクトがあるよ!』とデスクにやってきて、話を聞きました。映像の相談をするにも恐怖心や躊躇があるということに、僕も驚いたんですよ。それくらいこれまで相当大変な思いをされてきたんだと衝撃を受けました」
真鍋「そこから打ち合わせを重ねて、私たちも相当熱い想いを持っていましたが、皆さんの対応や企画に圧倒的な熱量があって素晴らしかったです」
『日大の良さとは何か』というインタビューの問いを、問い直す
──実際に企画が進み、卒業生へのインタビューをしていく中で、皆さんの中で何か変化や気づきはあったのでしょうか。
真鍋「当初は卒業生の皆さんに『日大の良さとは何か』を聞いてまわりたいと企画していたんですけど、結論からいうと、テーマが大きすぎました。私の問いの立て方がよくなかったと反省しています」
嶺「ドキュメンタリーのインタビューでは『この映像の問いは何なのか』というセントラルクエスチョンを立てることが非常に大事です。これがクリティカルかどうかで、インタビューの質も伝わるものも変わってくるためです。ただ、セントラルクエスチョンを立てるのは簡単なことではないので、実際にお話を聞く中でわかることがあるということを皆さんにもお伝えしていました」

嶺「僕の中で『日大の良さとは何か』で最初に浮かんだのは、多様性という言葉でした。学部やキャンパスの多様さなどもそういった志向のもとにあり、多様性が群を抜いているんじゃないかと直感的に思ったんです。ただ、『桜縁』をひと通り読んで感じたのは、多様性というよりも皆さん身軽だなということ。進路選択やキャリア選択などで、普通なら躊躇しそうなところをサッと選択するような身軽さを感じたんですよね。
そんな共通項がありそうだなという感覚的なところからスタートして、撮影が進んでいく中で、次第に問いが研ぎ澄まされていきました」
──そうだったのですね。

水野「今回、つながりの再構築を目指したいという想いから、私たちも卒業生に会いに行こうと決めていました。私は1人目の野木村さんの撮影で嶺さんに同行していて、その時のインタビューをよく覚えています。
『日大の良さ』について、率直にお伺いしてみたんですよ。そうすると、明確な答えは返ってこなくて。これをテーマに掲げてスタートしていたので、良いのかな……?っていう不安は正直ありましたね」
嶺「なにせ今回は13名を撮影するので、最初の1本を基準としてそれに沿って進めていきたく、野木村さんはかなり早めに撮影と編集をしました。
野木村さんの撮影は『日大の良さとは何か』というテーマだったとしたら、そこへの手応えはあまり強くはなくて、でもその代わりに、別のものすごく豊かなものが映ったんですよ。2人目の福岡さん、3人目の昆布さんと撮影を進めていく中で、次第に『ここを掘り下げていこう』と見えてくるものがあったのでその方向性で舵を切っていきました」
──校友会の皆さんとも会話をされながらだったと思いますが、皆さんもそういった方向性で進んでいくことに違和感はなかったですか?

真鍋「程なくして嶺さんが送ってくれた1本目の野木村さんの映像が、もう素晴らしくて。『日大の良さとは何か』というテーマは、頭でっかちだったなとその時に痛感しました」
嶺「野木村さんは、日大の建築学科で学ばれて30歳まで建築の会社にいらして、そこから夢を叶えたいということで家具職人に弟子入りするという、いわゆる脱サラ独立の方でしたね。
インタビューの中で『無駄はなかったと、言いたい感じがしますね』っておっしゃられていて。撮影時はまさかその言葉が映像のオチになるとは想定していませんでした。そういう計画では臨んでいなかったので。でも、インタビューの中で人生のキャリアの話になり、十数秒くらい沈黙した後に、ポツリと出た言葉がそれだったんですよ。それが、心から出た言葉だっていうのは感じました。
ドキュメンタリーやインタビューの映像は、最初と最後の一言がとても重要です。特に最後の一言は、メッセージのコアになります。ここしかない、と。
だからこの言葉へ向かって、それまでの10分間が組み立てられていく編集をしようと腹が決まりました。そして、この一言がこの先の12名の撮影において、『日大らしさ』の本質に近づく言葉なんじゃないかなっていうのは、当時はまだ確信は得られていませんでしたが、可能性を感じていましたね」
取材をする過程で自分たちも変化しながら生まれた、映像のコンセプト『道をひらく人』
──映像のコンセプトについても、細かいニュアンスを議論していった本プロジェクト。最終的に『道をひらく人』に決定するまでにどんなやり取りがあったのでしょうか。
嶺「最初の提案時の映像のコンセプトは『朝が来る』でした。日大の置かれている状況と、出演者の方々が失敗してもチャレンジし続けている姿勢。それらが重なって感じ取れるようにしたいと考えていて、夜明けから太陽が上っていくような映像表現をしようと提案をしていました。
ただ、数名の撮影を進行してみると、出演者が考えていることを伝えるのが良いのではないか。そうしたほうが、一番見る人に何か伝わるものになるんじゃないかと思ったんです。それで、コンセプトを立て直しますとお伝えしました」
真鍋「私たちも校友会本部事務局の中で、『朝が来る』はちょっと違うのではないかと議論していました。そこから嶺さんがある日、高村光太郎の道程の詩を持ってきてくださったんですよね」
”どこかに通じてる大道を僕は歩いてゐるのぢやない
僕の前に道はない
僕の後ろに道は出來る
道は僕のふみしだいて來た足あとだ
だから
道の最端にいつでも僕は立つてゐる”
– 高村光太郎『道程』より
真鍋「すごくぴったりで、感激したんです。日大の教育理念『自主創造』の中にある『自ら道をひらく』にもつながっているんですよ」
嶺「出演者のお話を聞きながらコンセプトを改めて確認していきたいっていう当初の意向通りでしたね。僕らや皆さんも、この制作過程で新しい発見をして、変化していったように思います。最終的に『道をひらく人』というコンセプトで決定しました」
共通するものを感じさせながら、“その人らしさ”を映す画づくり
──13名のインタビューを撮影していくにあたって、弊社としても統一感を出すための工夫をしながら臨んでいました。何か印象的だったことはありますでしょうか?
嶺「13名の皆さんのお仕事も経歴も撮影場所も異なる中で、共通するものを感じさせるような工夫をしています。全員にインタビューをするので、カメラのアングルなどビジュアル的な部分を含め必ずこの法則で撮影するという共通ルールを細かく決めていました。
その共通ルールに則りながらも、それぞれの“その人らしさ”を表現しないといけない。映像から静止画で切り出された時にも、言葉なしでちゃんとその人らしさが伝わるっていうのがインタビューの基本的な作り方なので、じっくり準備に時間をかけて撮っています」
真鍋「撮影準備の仕方は本当にすごかったですよ。カメラの位置や光の当て方に、ここまでこだわるんだって衝撃を受けました。今までの私が見てきた撮影とは違っていて、ミリ単位で細部にこだわりながら撮影をしてくださいました」
嶺「現場ディレクターとして弊社の小笠原、深津、そして社外のパートナー1名の計3名が中心となり撮影を進行していきました。彼らにとっても今回の撮影は、貴重な経験になっています。
インタビューで一番大切なことは、インタビュアーとインタビュイーが1対1の人間として人間関係を結べるかどうかなんですよね。映像に映るのはインタビュイーではなく、インタビュアーとインタビュイーの人間関係だと考えています。今回の撮影では、まさにそういった人間関係を映すということを身を持って体感をさせていただいたからこそ、学びが多かったと思います」
真鍋「撮影スタッフの皆さんがお若いので最初は不安に感じられる出演者もいらしたんですが、撮影現場でのプロとしての姿や振る舞いを見て安心してくださり、お互いがプロであるという信頼関係が結ばれていましたね。そういう空気感って映像にも映るんですよね。それも見どころです」
──撮影に同行して、卒業生のお話を直接聞く中で感じられたことはありますか?
水野「私は昨年まで学部の庶務課で勤務していて、実際に大学へのご意見をいただくこともありました。でも、皆さんのインタビューを通して、日大に対して良い印象を持っていて、大学に行ってよかったって言ってくれる方もいました。そんなお話を直接お伺いできて、本当によかったと実感しています」

三角「撮影が始まった頃、私はまだ日大で働き始めてから半年も経っていないくらいだったので、何もかもがはじめてのことで新鮮でした。本当に一人ひとりが、生き生きとしていらっしゃるのを目の当たりにして、私も精一杯生きたいなっていう気持ちになりましたね」
真鍋「それぞれの人生の中の良いところ、普遍的なところ、共通しているところ、本質的なところを本編に余すことなくまとめていただきました。それをぜひ見てほしいです」
──撮影後には毎回、プロジェクトチーム宛に真鍋さんからの想いをのせたメール(=通称、真鍋通信)が届いていたと聞いております。
真鍋「そうなんですよ。私が仕事を通じて思っていることを皆さんに素直に伝えても、きっと受け入れてくれるんだろうなと思い、撮影現場で感じたことを文面にして送りはじめました。13名の方を一気に撮影しているからこそ、気づきが多くて。私がこれまでの人生の中で感じていたことがお話を聞く中で、そして真鍋通信を書き続ける中で徐々に確信めいていきました」
嶺「最初は真鍋通信という名前も付いていなくて、返信不要ですと添えて送ってくださって。何回か送られてきた時に『真鍋通信、楽しみにしております』って返信をしたんですよね」
真鍋「みんなと一緒に全国のあちこちの現場に行ったので、途中から呼びかけは『旅の仲間たちへ』になりました。皆さんと一つのチームとして取り組めたことが本当に幸せでしたし、一緒に長い旅をしたような感覚です」
伊藤「13名にインタビューをしているのに、結果的に皆さん共通するところって一緒なんだっていう不思議な発見がありましたよね」
『道をひらく人』の完成と公開を終えて
──13本のインタビュー映像と、それをまとめた本編が公開となりました。プロジェクト全体を通して、皆さんのご感想を最後にお聞かせいただけますか。
真鍋「学内外含めた関係者にご覧いただいて『最高でした』『この想いを共有しながら、仕事をしていきたいです』といった感想が寄せられており、嬉しく思っています。
学びを継続し、学び合う喜びを知り、周囲と協働する人たちが、新たな価値を提示し、世界をちょっとだけ良くしていけるのだと実感しました。人生を楽しむということはこういうことなんだと、今回のインタビューや映像を通して確信できたことが幸せです。
映像が完成した後に嶺さんとメールでやり取りした『プロフェッショナルとは何か』という言葉に対する言語化がまさにという感じで印象に残っています」
“「プロフェッショナルとは何か?」という問いに対して自分なりの答えが見出せました。
プロフェッショナルとは、
「自分の持てる裁量を最大限に使い切り、結果にコミットし、そしてそこに責任を持つ人のこと」。
「裁量」という言葉と「プロフェッショナル」が結びついたのが今回の発見でした。
プロフェッショナルは、その裁量を最大限使い切り、自分にできることを全部やって、
良い結果を出したり、組織や社会を変えたりすることができる。期待を超えて感動を与えることをしている人。”
– 嶺のメールより
真鍋「今後の展開としては今回出演いただいた方々のように、何かしらのチャレンジをし続ける人たちをサポートするような制度をつくっていきたいですね。また、この映像とそこに映っている“価値”が世界に通用するのかに興味がありまして、ゆくゆく英語字幕を付けて世界の方にもご覧いただけるようチャレンジしたいです」

水野「大学職員は普段は事務的な仕事が多いので、今回は本当に大きなプロジェクトでしたね。この機会があったことにより、卒業生の方々やエレファントストーンさんを含めいろいろなつながりがつくれましたし、良い経験ができたと思っています」
三角「毎回別の側面が見えるようなおもしろくて深みのある映像に仕上がっていて、制作に関われたことを有り難く思っています。日大に赴任してきてまだそんなに期間が経っていませんが、さまざまな年代の卒業生にお会いして、皆さんとても親切で気さくで、日大を好きになるきっかけになりました。ありがとうございました」
エレファントストーン「日大校友会の皆様、この度はインタビューにご協力くださりありがとうございました!」
日本大学卒業生ドキュメンタリーシリーズ『道をひらく人』の映像は、こちらからご覧いただけます。
PROJECT
MEMBER
制作メンバー